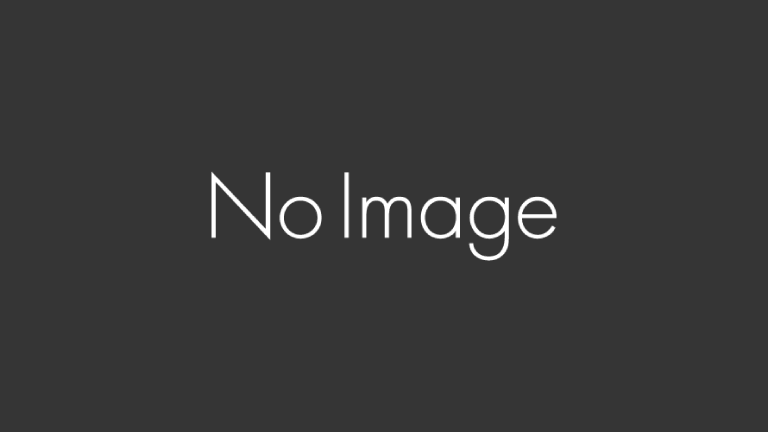ドリアンスケールとは?
さて、ドリアンスケールとはなんぞや、というところからまずは始めますが、大抵教本などに書いてある説明としては…
・CメジャースケールをD(レ)から始めたスケール
・マイナースケールの6度の音を半音上げたスケール
とか書いてある事が多いです。
ドレミファ…をレから始めると、ナチュラル・マイナー・スケールとほとんど同じ音列が得られますが、第6音のみが唯一違い、ナチュラル・マイナーに比べると半音高いです。
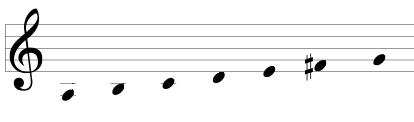
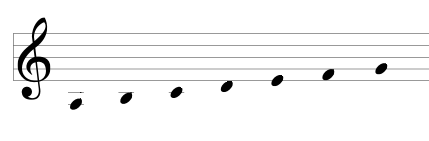
こちらはルートをAに統一して五線譜で表したものですが、ほとんど同じなのがわかります。
ちなみに、下はAマイナー・ペンタトニック・スケール。最初から第6音を弾かないのでこれだけ弾いてる分には元がどちらなのか分かりません。これが逆にペンタトニックが幅広く使えることの要因にもなるワケですが。
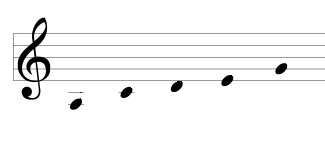
ドリアン・スケールの運指
さて、運指ですが、まず下の図をどうぞ。
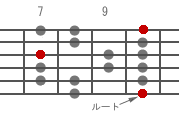
これはパッと見ると、Cメジャースケールです。実際に6弦8fをルートとして順に音を並べていくと、どう弾いても普通のCメジャースケールです。しかし、この図はルートの場所が違います。ルートはCではなく、D(10f)になっています。ルート(6弦10f)からルート(3弦7f)へ、1オクターブを弾いてからDm7をじゃら~んと鳴らしてみてください。
少々気持ち悪い気がするかもしれませんが、Dm7のコードを頭に浮かべながら何回も弾いてると、なんとなく自然な感じに聞こえてくるでしょう。と同時に、音の並びが普通のマイナースケールに比べてちょっと違うのが理解できるかと思います。上の話のとおり、ルートから見て6つめの音が、ナチュラル・マイナー・スケールに比べて半音高いので、その部分が違いとして実感できればしめたものです。この音の並びがドリアンスケールです。
つまり、Dドリアンを弾くということはCメジャースケールを弾く、ということと同じなのですが、バックに鳴っているコードがDmだったりDm7だったりしたときに、そのコードに合わせてDをルートとして違う名称で言い換えているに過ぎないわけです。
なら、Cメジャー・スケールだけ覚えればいいんでは?という声が聞こえてきそうです。これに対する答えは僕個人の考え方として二つあると思っています。
1.後ろのコード進行がDm7だけだったりする場合、Dのドリアン→Cメジャー・スケールを弾こう という読み替えが面倒
2.ドリアン・スケールとマイナー・ペンタトニックとの指板上の類似性を使って、フレーズを作りやすい
この辺じゃないでしょうか。まぁ、最終的には人それぞれだとは思いますが、わりとモードを単体で覚えている人は多いみたいです。
ダイアトニック・コードとドリアン・モード
DドリアンがCメジャー・スケールということは、Dドリアン・スケールでソロを取っている際のキーはCメジャーであると言えます。
同じく、Aドリアン=Gメジャー・スケールとなるので、キーはGメジャーということが出来ます。この際のコード進行においては……
Diatonic Chord (key in G)
| Gmaj7 | Imaj7 |
| Am7 | IIm7 |
| Bm7 | IIIm7 |
| Cmaj7 | IVmaj7 |
| D7 | V7 |
| Em7 | VIm7 |
| F#m7-5 | VIIm7-5 |
となります。これはKey in Gにおけるダイアトニックコードと呼ばれるもので、Am7はGキーにおけるIIm7に位置します。
Am7一発というシチュエーションで明確なコード進行がない場合、厳密にKeyが決まっているとは言えません。上の例ではキーGメジャーにおけるIIm7という扱いにしていますが、IIIm7(key in F)ともVIm7(key in C)とも取れるのです。m7一発の際にドリアンスケールを使うということは、そのm7コードを演奏者が意識的にIIm7と定義しているということになります。
同じように、VIm7ととらえると普通のマイナー・スケール(エオリアン・スケール)を使うことになるので、オーソドックスな音列のソロになります。
IIIm7ととらえた場合、フリジアン・スケールを使うことになりますが、これは稀です。イングヴェイがたまにやっています。同じように彼は7thコード一発を、普通のV7ではなく、敢えてIII7(マイナーKey上におけるV7)とすることでハーモニックマイナーを使ったりします。
この話は結構難しいですが、モード奏法の根幹をなす考え方なので、一歩上のアドリブを考えるための重要項目です。詳しく知りたいという方は拙著「六弦理論塾」をどうぞ。PC、タブレット、スマートフォンのアプリで読めます。